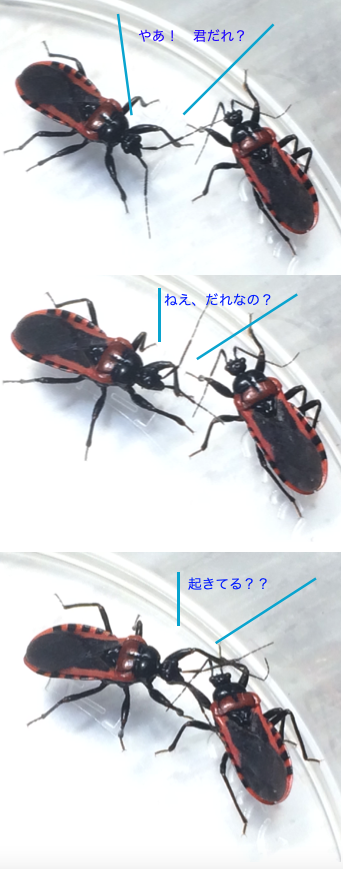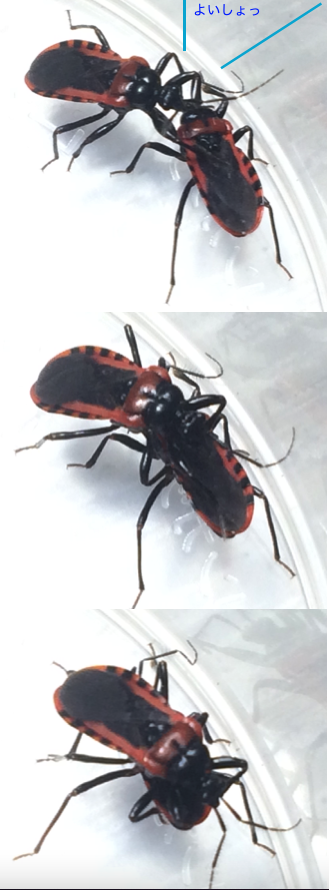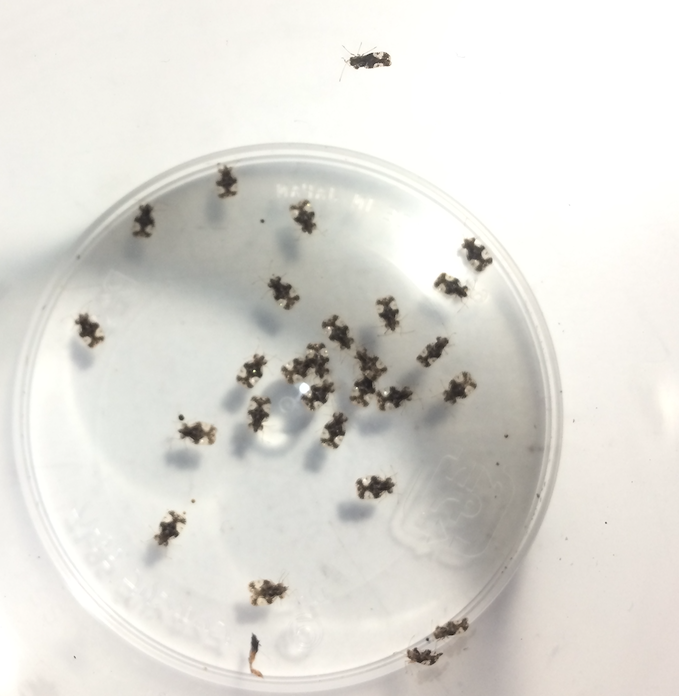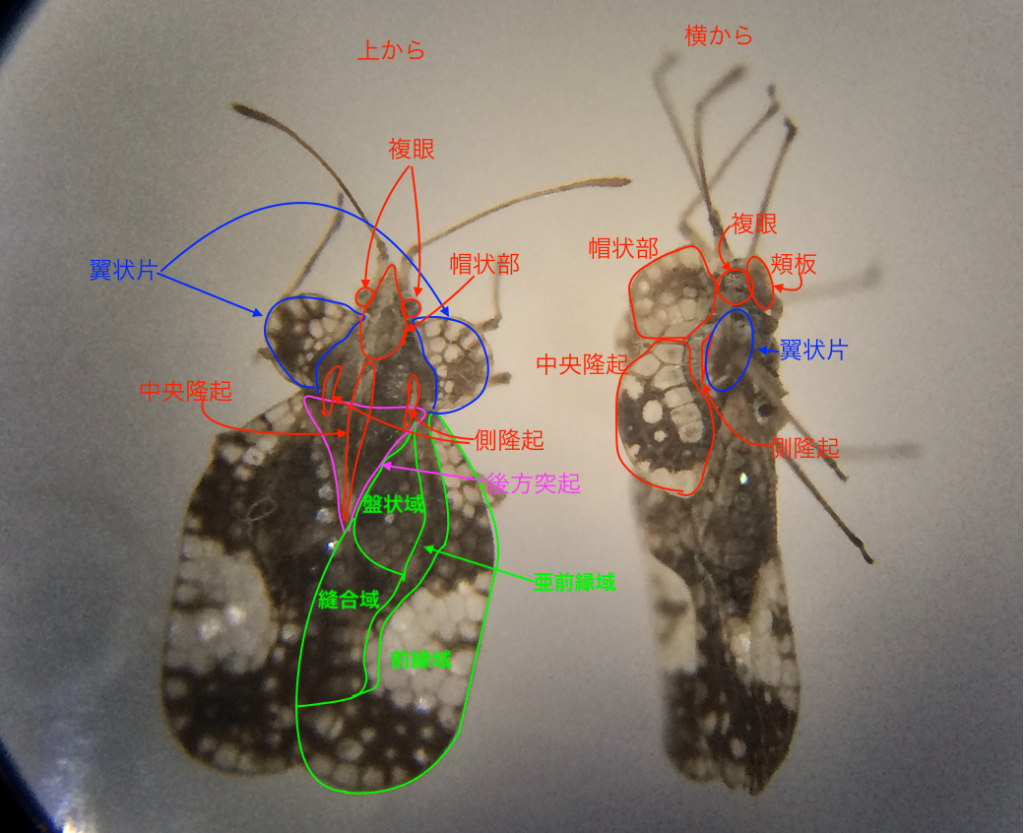ヘリカメムシ科ヘリカメムシ亜科。学名:Leptoglossus occidentalis。
体長15〜20mmくらい。
…………………………………………………………………………………………………………..
外来種です。
北米大陸原産の種類で、2008年くらいから日本に侵入してきたみたいです。
僕も、このカメムシ、最近まで全くみたことなかったのに、2019年ころから見かけるようになりました。
後脚がだいぶん特徴的ですね。

腿節の下面には とげとげが並んでる。
そして、何より、脛節の変な形!が気になる。
葉っぱ?みたいな形ですね。カッコイイ。
そして、白い斑点が一つ。
実は、同属に、アシビロヘリカメムシという、日本在来種がいるのですが、
その種類も似たような形の脚をしてます。

そして、背中の模様も興味深い。。

白い模様の部分を強調してみました(上写真)。
小文字の「h」のようにも見える。。

マツ「ヘリ(heri)」カメムシ の h ?
.
とはいえ、見た目は結構地味な、マツヘリカメムシさん。
でも、実は、、、


翅開くと、、
H・A・D・E
派 手 (終)