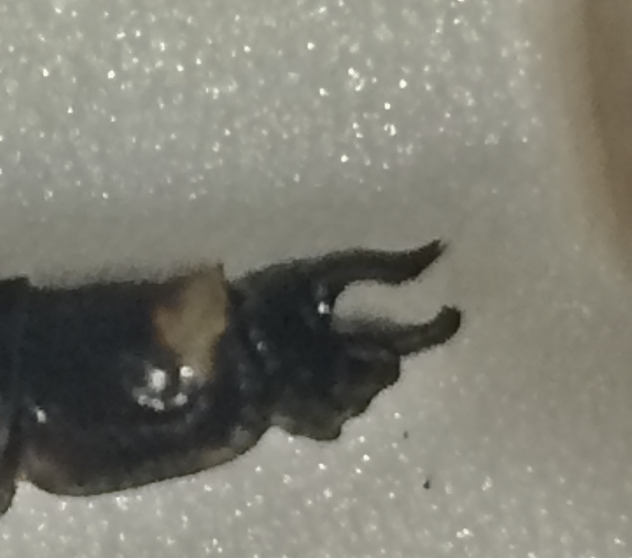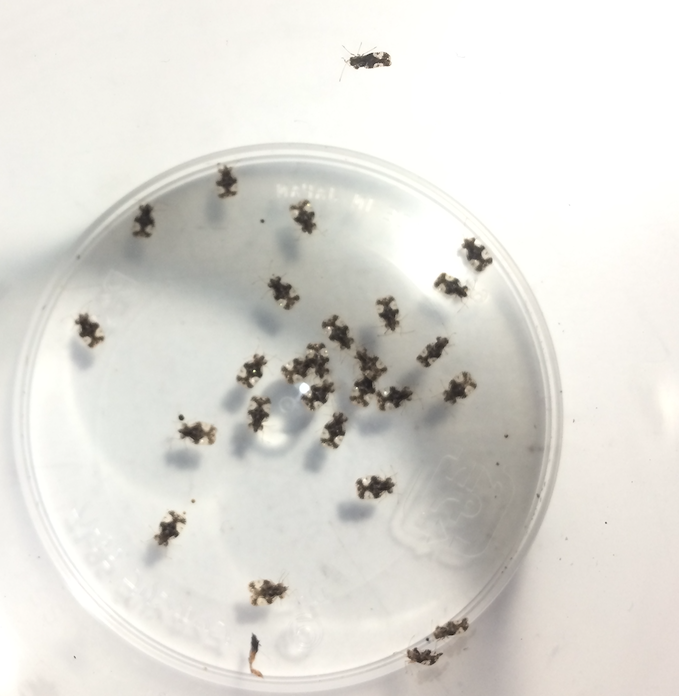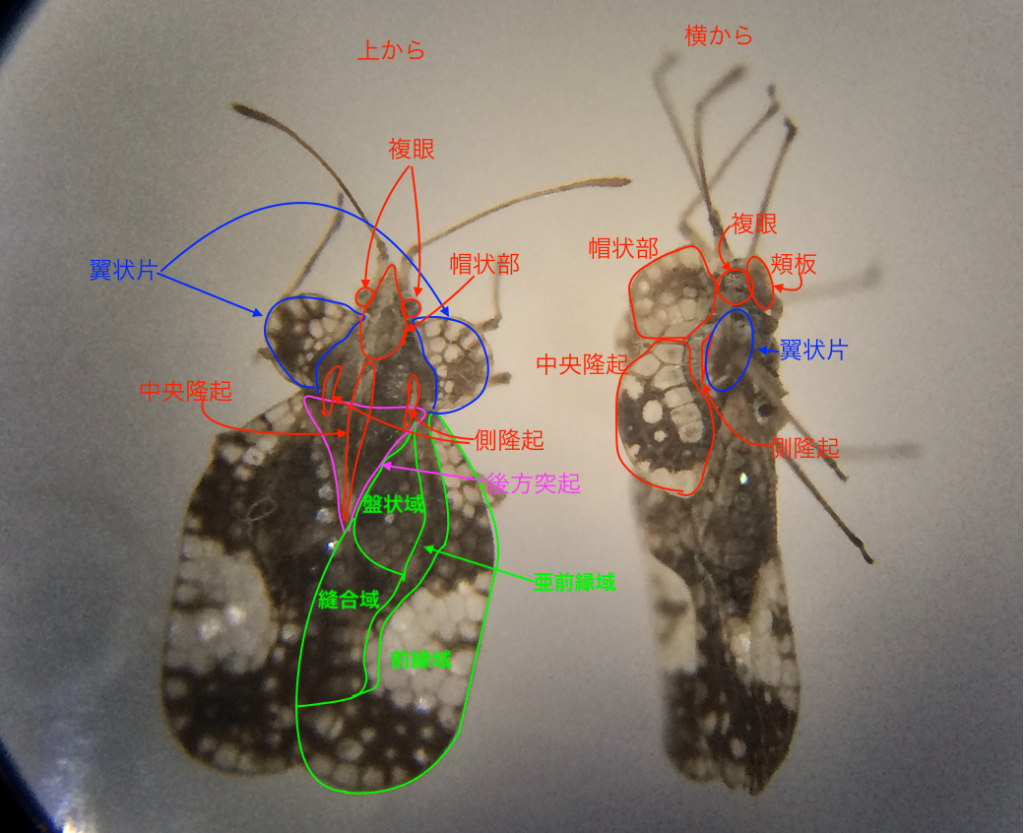はい、初めての昆虫採集記ですね。
このカテゴリでは、特に心に残った昆虫採集の記録を書かせていただきます。
………………………………………………………………………………………………….
2021年4月3日のこと。。
階段を駆け降り、網を持ち、容器をポケットに入れる。
ドアを開け、家の外に出た。
青い空が広がっている。。
自分の家の田んぼの方に走っていく。しゃがみ込む。
急に変な出だしで始まったなぁ、、(笑)
「おぉ、いるね〜、いますね〜」
↑僕の口癖である。
さて、何がいるかというと、マダラメバエさんである。

ぼやけた写真、、。撮影に集中してると、逃げられちゃうのでね。。
とか思ってたら、無事、逃げられました(笑)
ま、気にせず突き進んでいく。
タンポポに、何かいるかなぁ。
ヒメハナバチさんがたくさんいる。。でも、前回採集したから、今回は採集しない。
おぉ、ヌカカが結構いる。これは採集したいぞ。。
「あっ、逃げられた、。」「あっ、逃げられた、。」を繰り返して、ずいぶん時間が経ってから、やっとオスメス1組ずつ採集できた。意外と、素早い。
さらに進んでいく、。
ビロツリ(ビロードツリアブ)が毎年見られる場所に着きました。
今年は、まだ一匹も見ておりません。
と、、そこに、、
ビロツリみたいなハエが飛んできた!!
ん?ただのイエバエか、、って待てよ、なんか違和感あるぞぉ。
網をぎゅっと握る。こいつを逃したら、後で後悔するぞ。さぁっ、今だ!!
ビュン
入ったか??
おそるおそる網の中を見る。

いる。奴はいる。
容器に入れて、確認する。おぉ、今年初のたきにーだぁああああ。
※たきにー:ヤドリバエ科の呼称

カッコイイよおおおおおおお。
次に、虫がたくさん来る、青いネットのところへ。
「いるね〜、いますね〜」
↑僕の口癖、再登場。
カワゲラが結構いるが、カワゲラは採集しない。
あっ、オドリバエだあ、。Anacrostichusじゃないかっ。

初めて、青いお腹のオドリバエを採集しました。
いい虫がたくさんいて、一人でガッツポーズしました。
その後は、
「おっ、いるね〜、いますね〜」て一人で呟きながら、
キクビアオアトキリゴミムシなどを採集し、、、家に帰りましたとさ。。