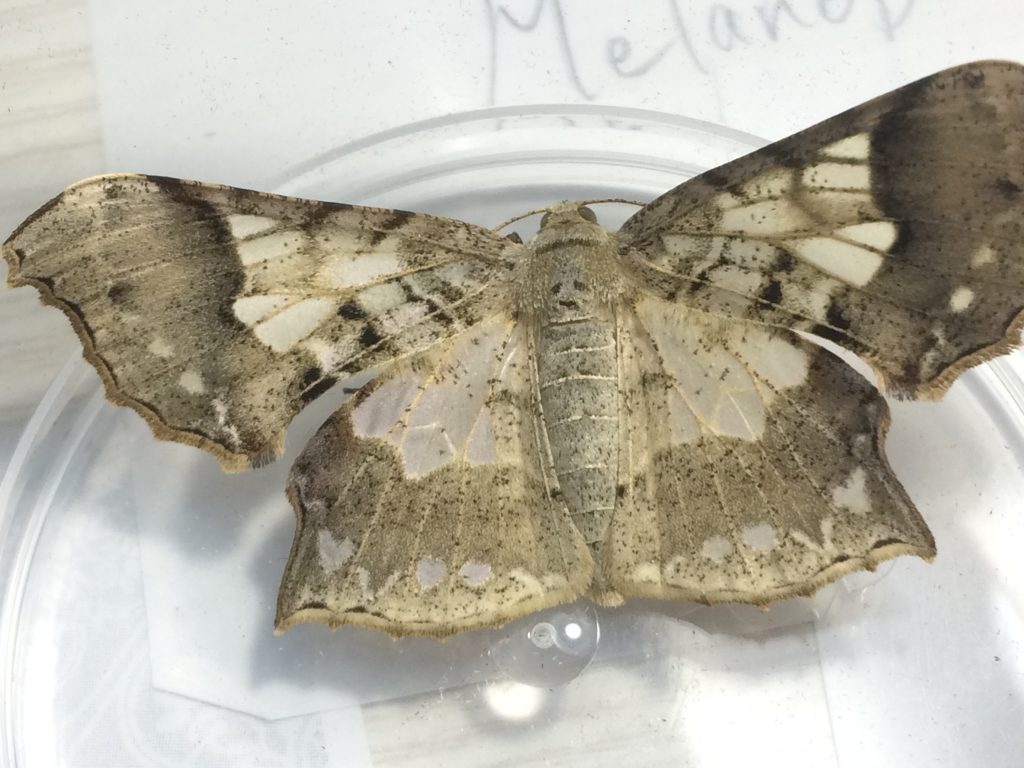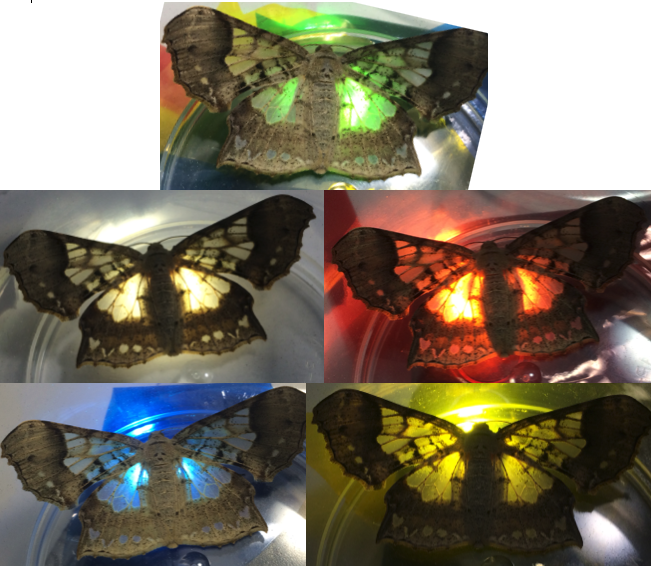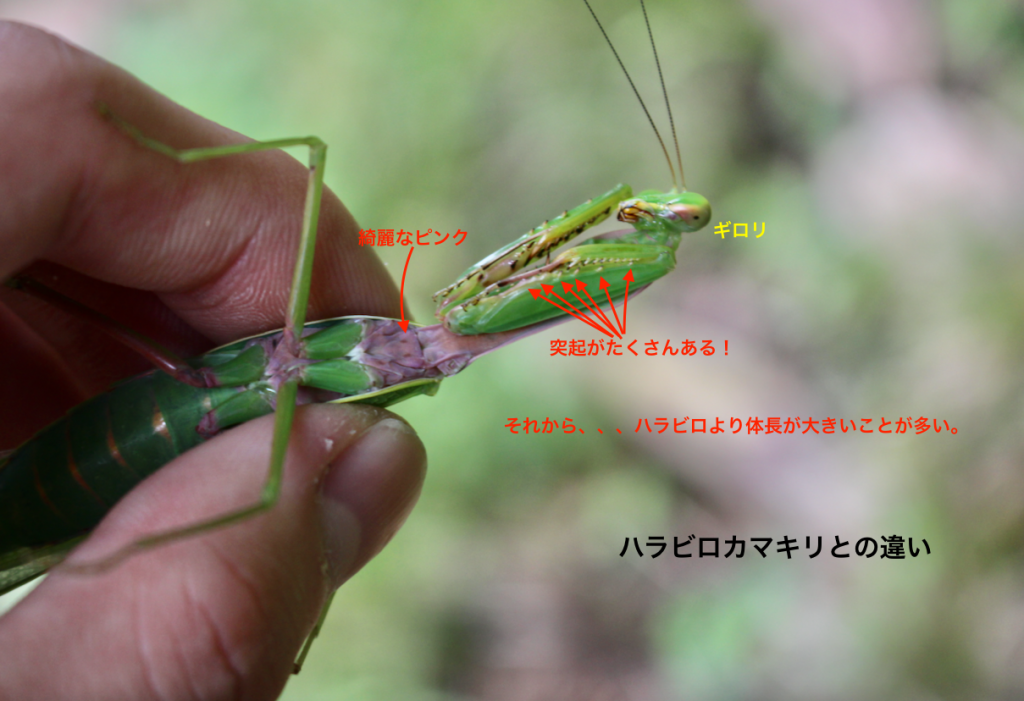2021.6.11撮影
2021.6.11撮影
ヤンマ科。体長70〜80mmくらい。学名:Anax nigrofasciatus。
……………………………………………………………………………………………………….
はいっ! 久しぶりの投稿ですねっ!
ちょっとテストとかあって勉強で忙しくて。。
今日は、クロスジギンヤンマさんについてです!

やはり、ヤンマのカッコ良さは、胸部からよく伝わってきますねぇ〜(^_^)
まるで、植物の葉っぱが詰まっているかのような生き生きとした緑色。
ちょっと色が薄くなっている部分が、線状になって存在しているので、
それが葉脈のようにも見えて、余計 葉っぱみたいですね。
そして、それを黒く太い筋で仕切っている。面白い。
そして、この筋も、ただの直線ではなくて、太くなったり細くなったりしていて、趣深いのです。
.
勿論、胸部以外にも魅力がたっぷりと詰まっています!
眼の色、いいですね。
上の写真では、青色と緑色が混ざり合って落ち着いた色になっています。
でも、それは、見る角度によって、鮮やかで若々しい水色に見えたりもします。
自然の美しさっ!!!
腹部は、オスだと水色、メスだと緑色の斑紋がありまして、これまたgorgeous。
.
ギンヤンマの場合は、クロスジギンヤンマと比べて、
胸部の黒筋がかなり細く、脚が赤く、腹部斑紋も違うので、容易に区別できます。
また、ギンヤンマとクロスジギンヤンマの交雑種として「スジボソギンヤンマ」というのがいて、こちらは結構珍しいです。 僕は見たことないです。😅